����o��o�c�w���A����̗��w�����s���ɂ��p���n���^�A�J�n���i�ׂ̑S�e�������J����
�p���n��/�A�J�n���Ɋ֗^�����w�����s���i�Q�O�P�S�N�x���_�j
��`�_���퍐�@�@�r���^���퍐�@�@�k���������w�� ��{���i���w���� ������������w���� �c�����ጳ�w�����⍲ �g�쒉�j�����w����
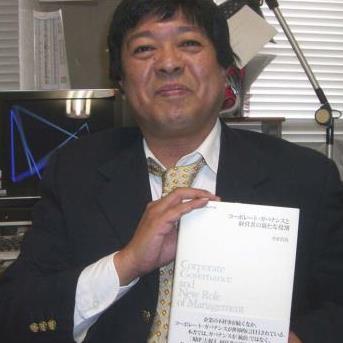 �@
�@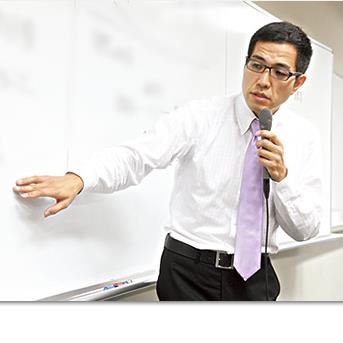 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
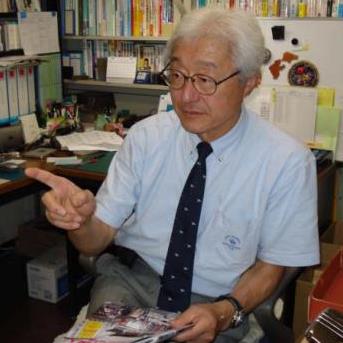 �@�@
�@�@ �@�@�@
�@�@�@
�@�@Information
�@�@�@�g �� �N �Y
�b�u�r :
�@�@Certified Value Specialist
�b�l�b :
�@�@Certified Management
�@�@�@ Consultant
�l�b�l�b :
�@�@Japan Master Certified
�@�@�@Management Consultant
���A���o�ϑ�w �o�c�w�� ����
.
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u��㍂�ق̔����Ƃ��̕��́E�]���v�ɖ߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�䂪�i�����n�ʕۑS�E�m�F�i�ׂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŏ��̉�ʂɖ߂�
�@��㍂�ق̔������̓��F��R ���ٔ����̔��f�F
�@�@�@�@�@�@���_�Q ��T�i�l��̑Ή�����@�ȉ��Q�s�ׂɊY�����邩�ۂ��ɂ���
�@�@�� �� 2015�N4��23���A��㍂�فA�������@�@ �� 2014�N9��30���A���n�فA������
�@�@�@�@�@�@����A���̑��_�P�A���_�Q�́A��ǂ��Ă��������B
�@�@�� ���_�P�D���C�C�p�A�J�g���s�̑����@�@�� ���_�Q�D�퍐��̌̈ӂɂ�鋤���s�@�s��
�@�@�u���_�Q�̑S����ʓǂ��āA�������ׂ��Ƃ��낪�Ȃ��A
�@�@�@���Ɏ����F�肨��ё��_�P�Ő������������Q�l�ɂ����A
�@�@�@��㍂�ق̔��f�����̓K�������������B
�@�@�@�Ȃ��A���_�P�̘J�g���s�̂Ƃ���́A
�@�@�@�@�@�T�i�����������̏������ʂɂ����āA
�@�@�@�@�@�@�@�咣���ׂ����e�Ə؋��ɂ�闧�Ȃǂɕs�\�������������̂�������Ȃ��B
�@�@�@���_�Q�ŁA�������u���C�����C�p�K���i�V�K���j���C�p� �@ �` �C ���[�����Ă�����
�@�@�@�@�@��������v�Ƃ̔����́A�u����̍K���v�ł���A�ٔ������b�オ�������A�Ɗ�������B
�R�@���_�i�Q�j�i�T�i�l�̓��C�����ւ̔C�p�\���ɑ����T�i�l��̑Ή����C
�@�@�@�@�@�@�@�������M�`�ɔ�������̂ł���C�T�i�l�ɑ����@�ȉ��Q�s�ׂɊY�����邩�ۂ�
�@�@�@�@�@�@�@�i��ʓI�����Q�y�ї\���I�����W�j�j�ɂ���
�@�i�P�j��T�i�l��`�́C����24�N10��15���C�T�i�l�ɑ��C��������3��1�i2�j�G(�A)�`(�G)
�@�@�@�@�̂悤�Ȑ�����������ŁC�����P�Q���ɊJ�Â��ꂽ�J���L�����������ψ����ɂ����āC
�@�@�@�@���ψ���̑��ӂƂ��āC�T�i�l�̒S��������Ƃ̂قƂ�ǂ́C�s�K�v���͕K�v�x���Ⴂ
�@�@�@�@�Ƃ������_�ɂȂ�C�T�i�l�̎��ƒS���v�����C�������E�ψ���ɒ�o���邱�Ƃ�
�@�@�@�@�ł��Ȃ��Əq�ׂāC�T�i�l�ɑ��C���C�����ւ��C�p�\�������ނ���悤���߁C
�@�@�@�@����ɁC�����P�U���ɂ́C�T�i�l�ɑ��C�T�i�l�����ƌv�揑�Ɂu�s���v������̂ŁC
�@�@�@�@���C�������C�p�葱��i�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��|�̃��[���𑗐M���Ă���B
�@�@�@-----------------------------------------------------------------------------
�@�@�������̐�����
�@�@����́A�X���Q�W���o�c�w��������ŁA
�@�@�@�@�퍐��`���A�S�w���ʂ́u���C�����C�p�K���i�V�K���j��������ׂ��Ȃ̂ɁA
�@�@�@�@�@�@���̋K�����U�����āA�����ɓK�p����K����������A
�@�@�@�@�@�@�����̎���ɑ��A��{���C�l���ɂ����Ă��K�p�������̂ƁA
�@�@�@�@�퍐��`�������Ă���B
�@�@���̋U�������K���̓��e�́A
�@�@�@�@�����̒S���Ȗڂ́A�J���L�������ψ���̏��F���K�v�Ƃ��A
�@�@�@�@�i�{���A������̐R�c�ɂ������Ă��Ă��邱�ƂŁA���F�@�\�͂Ȃ��B�j
�@�@�@�@�q��Ō����̒S���Ȗڂ�����ł��Ȃ��Ɠ������Q�l�̈�l�A
�@�@�@�@�@�@�퍐��`�w�������u�R�J�N���ƌv��v���쐬�����v
�@�@�@�@�u���E�ψ���ɒ�o���邩���Ȃ����́A�w�����ł���퍐��`�����߂��v�Ȃǂł���B
�@�@�����U�������K���Ɋ�Â��āA�퍐�r�����A�J���L�������ψ��S���̑��ӂƂ��āA
�@�@�@�@�����̒S���Ȗڂ͕K�v�x���Ⴂ�Ⴕ���͕s�v�A�s�J�u�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@���������āA�u�R�J�N���ƌv��v�͍쐬�ł��Ȃ��B
�@�@�@�@�V�K���́u���Ɂv�ɓK�����Ȃ��A�u�P���Ȗڂ̂Q���d���J�u�v�����Ă���A
�@�@�@�@�@�@���w���[�������Ȃ��l���i������d�|�����͔̂퍐��`��ł���j�Ȃ�
�@�@�@�@�U�̗��R�������A
�@�@�@�@��������ƂɁA�P�O���P�T���A�퍐��`�������ɓ��C�\�����ނ𔗂�������A
�@�@�����́A�u�V�K���v�Ɋ�Â��āA���E�ψ���ŐR�c���A
�@�@�@�@�����Ő��E����Ȃ���A����ŗǂ��A�ƌŎ��A
�@�@�@�@�퍐��`�́u�w�͂���v�Ƃ����đސȁA
�@�@���̗����ɁA���i�w���i���E�ψ���ψ����j�ɖʉ�A
�@�@�@�@�u���E�ψ���͐\�����ނ�R�����A�u���ނ̕s���v����ꍇ�͎��Ȃ��v
�@�@�@�@�Ƃ̃A�h�o�C�X���A������u���O���c�v�Ə̂��A
�@�@�����́u�R�J�N���ƌv��v�̓J���L�������ψ���̕]���̂悤�ɕs�K�v�E�s�J�u�ł��邩��A
�@�@�@�@���E�ψ���́u���Ȃ��v���ޕs���̂��߁A��o���Ȃ��A�ƌ����ɂP�U�����[�������A
�@�@�@�@���̌�̋�����ŁA���i�ψ������u���Ȃ����Ɓv�����肵���A�ƕA
�@�@��������o�[���u���ނ̕s���v�Ƃ͉����Ƃ̎���ɂ͓������A
�@�@�@�@�c��ɋ������Ă��Ȃ��ȂǂƓ˂��ς˂Ă���B
�@�@���������āA���̓��Y�����́A�퍐�炪�s�@�s�א��s����\�����Ă���B
�@�@�@-----------------------------------------------------------------------------
�@�i�Q�j�A�@�����Ō�������ɁC��������R�̂P�i�Q�j�A�ŔF�肵���Ƃ���C�T�i�l�����C�����ւ�
�@�@�@�@�@�@�C�p�\���ɍۂ��Ē�o�����u�R���N�u�`�v��v�ɋL�ڂ��ꂽ�u�`���e���́C
�@�@�@�@�@�@�T�i�l�̕����Q�S�N�x�̍u�`���e���Ƃقړ��l�̂��̂ł����C�T�i�l���u�R���N�u�`
�@�@�@�@�@�@�v��v�ɋL�ڂ����u�`�̂����C�u�O�����u�ǁv�́C�T�i�l�������Q�R�N�x�ɒS������
�@�@�@�@�@�@�S�����Ɛ��̕s����₤���߂ɁC�����Q�Q�N�����C�J���L�����������ψ���̍\������
�@�@�@�@�@�@��������T�i�l��`����̈˗����āC�����Q�R�N�x����T�i�l���S������悤��
�@�@�@�@�@�@�Ȃ����o�܂�����C�܂��C�]�O��P���݂̂ŊJ�u���Ă����u���l�b�g���[�N�_
�@�@�@�@�@�@�T�E�U�v�y�сu���o�����[�G���W�G�A�����O�v���C�����Q�R�N�x�����Q���ł�
�@�@�@�@�@�@�J�u���邱�ƂɂȂ����̂��C���l�̌o�܂ɂ����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�����āC�����Q�S�N�x�̎��ƒS���v��ł��C
�@�@�@�@�@�@���ꂪ�T�˂��̂܂ܓ��P����Ă���C�܂��C�����Q�S�N�x�܂ł̊ԂɍT�i�l���S������
�@�@�@�@�@�@�����u�`�̓��e���ɂ��āC�J���L�����������ψ���ɂ����āC�K�v�x���Ⴂ�Ȃǂ�
�@�@�@�@�@�@�������������߂�ӌ����o���ꂽ���Ƃ͂Ȃ������Ƃ����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@���̂悤�Ȏ���ɂ��ƁC�����Q�R�N�x�̍T�i�l�̎��ƒS���v��́C
�@�@�@�@�@�@�T�i�l�̒S�����Ɛ��̕s����₤���߂̗Վ��̂��̂ł������\��������C
�@�@�@�@�@�@�����Q�S�N�P�O���P�Q���̃J���L�����������ψ���ɂ����āC������p�����邱�Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�����Ƃ���邱�Ǝ��͕̂s���R�ł���Ƃ͂����Ȃ����̂́C
�@�@�@�@�@�@�����ŁC��T�i�l�r���́C���R�ɂ�����{�l�q�Ԃɂ����āC�J���L�����������ψ�����
�@�@�@�@�@�@��������T�i�l�r�����g���C�T�i�l���]�O�S�����Ă����u�`�̓��e�𗝉����Ă���
�@�@�@�@�@�@�킯�ł͂Ȃ��C�F�X�Ȑ�U���삩��I�o����Ă���J���L�����������ψ���̑��̈ψ�
�@�@�@�@�@�@������C�T�i�l�̍u�`�̓��e�ɂ��Ă̎��������Ȃ������ȂǂƏq�ׂĂ���
�@�@�@�@�@�@�i���q�⒲���Q�Q�`�Q�R�Łj�C
�@�@�@�@�@�@���̂��Ƃ��炷��ƁC���ψ���̈ψ��̒��ɁC
�@�@�@�@�@�@�T�i�l�̍u�`���e�𗝉����Ă����҂������Ƃ͕K�������F�ߓ�B
�@�@�@�@�@�@��������ƁC�����̃J���L�����������ψ���ɂ����āC
�@�@�@�@�@�@�T�i�l����o�����u�R���N�u�`�v��v�ɋL�ڂ���Ă����u�`�ɂ��āC
�@�@�@�@�@�@�s�K�v���͕K�v�x���Ⴂ�Ƃ��ӌ��ň�v�����Ƃ����̂́C
�@�@�@�@�@�@���˂ł���Ƃ̈�ۂ��ʂ������C�s���R�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�@�@-----------------------------------------------------------------------------
�@�@�������̐�����
�@�@�퍐��`�A�퍐�r����́A�������������r�����邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă��邩��A
�@�@�@�@��㍂�ق��u�s���R�v�Ƃ̈�ۂ���̂́A���R�Ǝv���B
�@�@�Ȃ��A�������ʂ��A���U�������A
�@�@�@�@�퍐��`�A�퍐�r���̐q��ł́A�w�ǂ��u�K���v�ɔ����Đ��s���Ă����s�����e��
�@�@�@�@���������K�������炵�Ă��邩�̂悤�ɒq���Ă���B
�@�@�w�̂�������A���R�ƉR�����āA
�@�@�@�@�{���Ɋw���ɗǂ��u�`���ł���̂��A�^��Ɏv�킴������Ȃ��B
�@�@�@-----------------------------------------------------------------------------
�@�@�@�@�C�@�܂��C��T�i�l�r���́C���R�ɂ�����{�l�q��ɂ����āC�T�i�l�̒S�����Ă����Ȗڂ�
�@�@�@�@�@�@��u�Ґ��́C���Ȃ��͂Ȃ����ނł������|���q���Ă����i���q�⒲���Q�V�Łj�C
�@�@�@�@�@�@���ɁC�T�i�l�̒S������u�`���e�ɖ�肪�������̂ł���C�T�i�l�́u�R���N�u�`
�@�@�@�@�@�@�v��v�̓��ۂɂ��Č��_���o���ȑO�ɁC
�@�@�@�@�@�@���̉ȖڂɕύX���邱�Ƃ��\�ł��邩�ۂ��ɂ��Ă̌������s����̂����R��
�@�@�@�@�@�@����Ƃ���C���̂悤�Ȍ������s��ꂽ�`�Ղ��Ȃ��܂܁C�J���L�����������ψ����
�@�@�@�@�@�@�����āC�킸���P��̐R�c���s��ꂽ���ʁC�J���L�����������ψ���̑��ӂł����
�@�@�@�@�@�@���āC��T�i�l��`����T�i�l�ɑ��C���C�����ւ̔C�p�\�������ނ���悤�\���ꂪ
�@�@�@�@�@�@����Ă��邱�Ƃ��C�ɂ߂ĕs���R�ł���B
�@�@�@�@�E�@�ȏ�̂悤�Ȏ�����l������ƁC��T�i�l�炪�咣����C�T�i�l�̎��ƒS���v���
�@�@�@�@�@�@�u�s���v�ɂ��Ă̗��R�́C�����I�ȍ����Ɋ�Â����̂ł���Ƃ͔F�ߓ�C�ނ���C
�@�@�@�@�@�@�J���L�����������ψ���̑��ӂƂ��čT�i�l�ɑ��Đ������ꂽ����
�@�@�@�@�@�@�i��������R�̂P�i�Q�j�G�i�A�j�`�i�G�j�̎���j�́C
�@�@�@�@�@�@�T�i�l�̔C�p�\�������ۂ��邽�߂̌����ɂ����Ȃ����̂ł��������Ƃ����F����C
�@�@�@�@�@�@���̐��F���ɑ����؋��͑��݂��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@��������ƁC�T�i�l�̓��C�����ւ̔C�p�\���ɂ��ẮC����24�N10��12�������C
�@�@�@�@�@�@�J���L�����������ψ���̈ψ����ł�������T�i�l�r���ƁC�w�����Ƃ��ē��C�����ւ�
�@�@�@�@�@�@�C�p�\���������҂̎��ƒS���v�����C�������E�ψ���ɒ�o����Ӗ����Ă���
�@�@�@�@�@�@��T�i�l��`���C���݂Ɉӂ�ʂ�����ŁC��L�̂悤�Ȍ�����݂��āC���s�K����C
�@�@�@�@�@�@��T�i�l��`�ɂ����čs�����Ƃ��\�肳��Ă���C�����ψ����y�эT�i�l�Ƃ̊Ԃ�
�@�@�@�@�@�@���ƒS���v��̍쐬�Ɋւ��鋦�c���s�����Ƃ����ۂ��C
�@�@�@�@�@�@�T�i�l���C�p�\���̎葱��i�߂邱�Ƃ���]�����ɂ�������炸�C�C�p�\���̎葱��
�@�@�@�@�@�@�����Đi�߂Ȃ��������̂ƔF�߂�̂������ł���B
�@�@�@�@�G�@���̓_�Ɋւ��C��T�i�l��́C��T�i�l��`�ɂ����āC�T�i�l�̓��C�����ւ�
�@�@�@�@�@�@�C�p�\���ɂ͏��ނ̕s��������Ɣ��f���C���Ԃ����ւɐi�߂邽�߁C
�@�@�@�@�@�@�O��Ɉˋ����čT�i�l�ɑ��Đ\������艺����悤���������݂����̂́C
�@�@�@�@�@�@�T�i�l������ɉ����Ȃ��������߁C��ނȂ����C�������E�ψ���̈ψ����ɑ��k��
�@�@�@�@�@�@�������̂ł���C��T�i�l��`�́C���C�������E�ψ���Ɏ��ƒS���v����o��������
�@�@�@�@�@�@�ƕ]�����ׂ��ł���Ƃ��C���ƒS���v��̍쐬�����́C�w�����ł�������T�i�l��`��
�@�@�@�@�@�@����C�w�����̌���͋�����ł̌���ł�����Ǝ咣����B
�@�@�@�@�@�@�������C��T�i�l��`�����C�������E�ψ�����ψ����ɑ��k�������݂̂ŁC
�@�@�@�@�@�@��T�i�l��`�����C�������E�ψ���ɍT�i�l�̎��ƒS���v����o�������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�Ȃ�Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���C�܂��C���ƒS���v��̍쐬�������w�����ł�����
�@�@�@�@�@�@��T�i�l��`�ɂ���Ƃ��Ă��C���̌��肪������̌���ł���Ƃ������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�ł��Ȃ����Ƃ����炩�ł�������C
�@�@�@�@�@�@��T�i�l��̏�L�咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�i�R�j��������R�̂P�i�Q�j�G�ŔF�肵���C��T�i�l��`���T�i�l�ɓ��C�����ւ̔C�p�\��������
�@�@�@�@����悤���߂��ۂ��������e�́C���ɔF�肵���Ƃ���C�����I�ȍ����������C
�@�@�@�@�����ɂ����Ȃ����̂ł����������ɁC�T�i�l�����C�����ւ̔C�p�\���ɍۂ��Ē�o����
�@�@�@�@�u���C�����C�p�����v(�b5)�y�сu�{�w�ɂ������E���v(�b6)�̋L�ړ��𑍍�����ƁC
�@�@�@�@�T�i�l�́C��������Q�̂P�i�Q�j�A�̌��s�K����Q���i�P�j�y�ё�S���̏��v��������
�@�@�@�@�������̂Ɖ������B
�@�@�@�@��������ƁC�T�i�l�́C���C�����ւ̔C�p�\�����s���C���s�K���ɒ�߂�ꂽ����̎葱��
�@�@�@�@��Â��āC�C�p�Ɋւ���R�����邱�ƂɊւ��āC
�@�@�@�@�@����ی�ɒl���闘�v��L���Ă����Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�i�S�j�ȏ�ɂ��ƁC
�@�@�@�@�T�i�l�̓��C�����ւ̔C�p�\���ɍۂ��āC��T�i�l��`�y�є�T�i�l�r���́C
�@�@�@�@�������čT�i�l�̖@����ی�ɒl���闘�v��N�Q�����Ƃ������Ƃ��ł���̂ŁC
�@�@�@�@��T�i�l��`�y�є�T�i�l�r���̍s�ׂ́C
�@�@�@�@�T�i�l�ɑ���C�̈ӂɂ���@�ȉ��Q�s�ׂł���Ƃ������Ƃ��ł��C
�@�@�@�@��T�i�l��`�y�є�T�i�l�r���́C�T�i�l�ɑ��C�s�@�s�ׁi���@�V�O�X���j�Ɋ�Â�
�@�@�@�@���Q�����`�����ׂ����ƂɂȂ�B
�@�@�@�@�����āC��T�i�l��`�y�є�T�i�l�r���̏�L�̍s�ׂ́C
�@�@�@�@��T�i�l��w�̋Ɩ��̎��s�ɂ��čs��ꂽ���̂ł���ƔF�߂��邩��C
�@�@�@�@��T�i�l��`�y�є�T�i�l�r���̎g�p�҂ł����T�i�l��w�́C
�@�@�@�@���@�V�P�T���P���Ɋ�Â����Q�����`�����ׂ����ƂɂȂ�B
�@�i�T�j�Ȃ��C��T�i�l��́C�T�i�l�����C�������E�ψ���Ő��E�����\���͊F���ɋ߂�����
�@�@�@�@�Ǝ咣����B
�@�@�@�@�������C��L�̂Ƃ���C�T�i�l�́C���C�����ւ̔C�p�ɂ��āC���s�K���ɒ�߂�ꂽ
�@�@�@�@����̎葱�Ɋ�Â��ĐR������@����ی삳�ꂽ���v��L���Ă���C
�@�@�@�@���ۂɏ���̎葱�Ɋ�Â��ĐR�����Ă��Ȃ��ȏ�C���̗��v��N�Q���ꂽ��
�@�@�@�@�����ׂ��ł����āC�T�i�l�����C�����ɔC�p�����\���̒��x�́C
�@�@�@�@���̔��f�����E���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�擪�ɖ߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�Q ��T�i�l��̑Ή�����@�ȉ��Q�s�ׂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Y�����邩�ۂ��֖߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u��㍂�ق̔����Ƃ��̕��́E�]���v�ɖ߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�䂪�i�����n�ʕۑS�E�m�F�i�ׂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŏ��̉�ʂɖ߂�