◆大経大経営学部、特定の歴代学部執行部によるパワハラ/アカハラ訴訟の全貌を情報公開する
パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
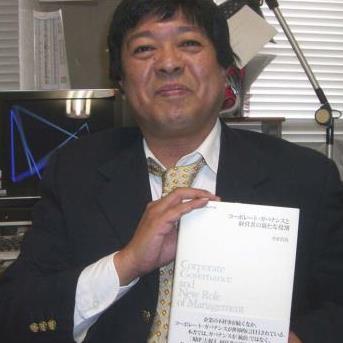
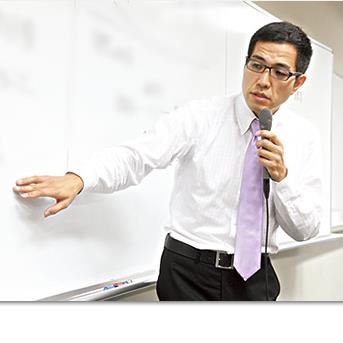


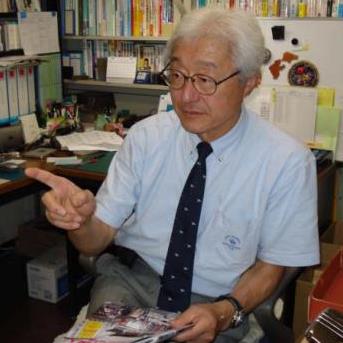


Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
●「大阪高裁の判決とその分析・評価」に戻る
吉井が訴えた地位保全・確認訴訟へ
最初の画面に戻る
大阪高裁の判決文の内:第3 当裁判所の判断: 認定事実
⇒ ⇒ 2015年4月23日、大阪高裁、判決文 ⇒ 2014年9月30日、大阪地裁、判決文
是非、次の争点1、争点2は、一読してください。
⇒ 争点1.特任任用、労使慣行の存在 ⇒ 争点2.被告らの故意による共同不法行為
ここでは、「第3 当裁判所の判断: 認定事実」を逐次抜粋し、
裁判所の認定に疑義ある場合、当該箇所を分析・評価することを目的とする。
.
検 索 項 目
1.「3ヵ年講義計画」の認識(第3当裁判所の判断1(2)カ)
2.被告井形による特任申請辞退要請の認識(第3当裁判所の判断1(2)キ)
3.被告池島報告の原告の担当科目の認識(第3当裁判所の判断1(2)エ)
1.「3ヵ年講義計画」の認識(第3当裁判所の判断1(2)カ)
----------------------------------------------------------------------------------------------
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(前記第2の3の前提事実のほか,証拠(後掲の各証拠,甲22,乙26,27,
原審控訴人本人,原審被控訴人池島本人,原審被控訴人井形本人)
及び弁論の全趣旨を総合すると認められる事実)
(1)後記(2)のとおり付加・訂正するほかは,
原判決18頁2行目から21頁20行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)ア 原判決18頁26行目から19頁1行目にかけての「(乙28の1ないし6の2)」を
「(乙28の1~4,乙28の5の1・2,乙28の6の1・2)」と改める。
イ 原判決19頁9行目の「授業計画書」を「授業担当計画」と改める。
ウ 原判決20頁11行目の「平成23年度が1名,」を削除する。
工 原判決20頁12行目の末尾に続けて「なお,平成18年度から平成25年度までの
間に,特任教員任用申請を行ったにもかかわらず,任用されなかったのは,
控訴人のみである。」を加える。
オ 原判決20頁15行目の「授業計画」を「授業担当計画」と改める。
--------------------------- <原告が問題視する、当該部分> -----------------------------
力 原判決20頁17行目の末尾に続けて「控訴人は,平成24年9月末頃,被控訴人井形に
対し,「3ヵ年講義計画」等の所定の書面を提出し,特任教員への任用を希望する意向を
明らかにした。
控訴人作成に係る「3ヵ年講義計画」に記載された平成25年度から平成27年度までの
間の講義の内容等は,控訴人の平成24年度のものとほぼ同様のものであり,
「情報ネットワーク論Ⅰ・Ⅱ」,「情報バリューエンジニアリング」及び「経営情報論」を第1部
と第2部で開講し,「外国書講読Ⅰ・Ⅱ」を第1部で開講するものとされていた(甲7)。
控訴人の講義内容については,平成23年度の授業担当計画を決めるに際して,控訴人の
平成23年度の担当授業数(持ちコマ数)が,平成21年9月に定められた申し合わせに
基づく所定の数よりも1.5コマ分不足する状況になっていたことから(控訴人は平成22年
度は国内留学中であり授業を担当していなかった。),
その対応策についてカリキュラム検討委員会で検討が行われた結果、当時、カリキュラム
検討委員会の構成員であった被控訴人井形が,平成22年8月6日,控訴人に対し,
①北浜イブニング科目として既存の科目を開講する(0.5コマ),
② 「経営学特殊講義(環境経営論)」を担当する(0.5コマ),
③ 「外国書講読」を担当する(0.5コマ)
のいずれかについて,合計1コマ分を担当するよう依頼するとともに,
④当時控訴人が担当していた講義科目を第2部で開講することも可能である
との提案をしたことから,
控訴人がこれに応じて,「外国書講読」及び「経営学特殊講義(環境経営論)」を担当する
とともに、「情報ネットワーク論Ⅰ・Ⅱ」及び「情報バリューエンジニアリング」を
第2部でも開講することとしたものであり,平成24年度の授業担当計画も,
概ねこれを踏襲したものであった(甲7,16,乙22)。
なお,平成24年度までの間に控訴人が担当していた講義の内容等に関しては,
カリキュラム検討委員会等において,必要度が低いなどとして是正を求める意見が
出されたことはなかった。」を加える。
--------------------------- <原告が問題視する理由> -------------------------------------
「平成21年9月に定められた申し合わせに基づく所定の数よりも1.5コマ分不足する
状況になっていたことから、その対応策について①②③に加え、④当時控訴人が担当して
いた講義科目を第2部で開講することも可能」
この記述から、大阪高裁は、次の「申し合わせ」(乙22)を判断の根拠としたと理解される。
「専任教員の担当コマ数についての申し合わせ」(乙22)に記載の内容、
「専任教員は原則週4コマ以上担当しなければならない(就業規則)が、
標準担当コマ数は大学院開講科目を含め5~8コマとする」
しかし、「申し合わせ」は「申し合わせ」に過ぎず、これで判断することは誤りである。
(a) 就業規則の4コマを超えるコマ数を講義すること、これが唯一の条件であり、
「申し合わせ」には拘束力が全く無く、
次のデータに示されるように、多くの教員はこれに拘束されていない。
⇒
経営学部における、2012年度担当者別講義コマ数(大学および大学院)
⇒
2011年度と2012年度講義実績(原告)
(b) 他学部では、教員の負担を増やすこのような申し合わせは無いと聞いている。
これと同様に、20名近くの期限付き教員が経営学部に在籍しているが、他学部は皆無である。
この2つが示す意図は、山田文明学長補佐の発言(甲24、その音声データは甲29)に
あるように、人件費の負担を抑えるという名目のもとで、立場の弱い期限付き教員を
雇用することにより、学部執行部の発言力と統制力を高めるところに狙いがある。
⇒
2003年度~2012年度における、期限付教員人数の推移
(c) 「④担当していた講義科目を第2部で開講することも可能」を
申し合わせに基づくモノと理解されているところが大きな理解ミスである。
これは、
被告井形に、以前から2部科目の開講をお願いしていた経緯と、
被告らの原告の負担を増やすという意図が合致して、
原告の希望が実現したものである。
「1部担当科目合計2.5コマで就業規則の4コマを充たすには1.5コマ不足する。」に関しては、
(経営情報論、情報バリューエンジニアリング、情報ネットワーク論ⅠとⅡ、演習Ⅰ)
原告の1部科目を2部で開講するだけで、4.5コマとなり、就業規則上全く問題はない。
大阪高裁は、このような実情を知ることは難しく、
申し合わせ事項を充足するためには、次の1コマを加える必要があるとしている点である。
外国書購読(0.5コマ)、環境経営論(0.5コマ)
このような「学内規程にそった正しい実態把握ミス」といったリスクを回避して、
誤りなき判決を下せる工夫、
例えば、双方に議論させる、疑問を投げかける、資料を出させるなど
の工夫がほしい、というのが原告の主張である。
⇒
被告井形に(2008年6月、副学部長兼カリキュラム委員長)に、
「2009年度2部カリキュラムヘの担当科目申請書」を提出
補足すると、
(c)-1.外国書購読はⅠとⅡの1コマで完結するところをわざわざ0.5コマと指定しているところ、
(c)-2.原告は著書も出版し、研究対象としている「環境経営論」、
この講義を新たに開講する負担は、外国書購読の比では全くないこと
留学復帰後、新規採用のタイミングは普通、コマ数が不足することが多く、
外国書購読や就職活動支援(インターンシップ)などを持たせて、
就業規則の4コマを充たさせる、という手続きが通常の手続きである。
(c)-3.上記2つより、外国書購読(1コマ)とせず、環境経営論を選択させる学部執行部の意図
(パワハラ)を理解していただきたいところである。
(c)-4.「④担当していた講義科目を第2部で開講することも可能」と明記されているが、
これを1部科目を2部科目として開講してもよいと解釈するのが普通であるが、
被告井形および被告池島は、
原告が勝手に1部科目を2部の時間帯に重複講義しているとして、
規定を遵守しない人物であり、特任任用から除外すべき人物としている。
実際は逆で、教学ルールを無視しているのは、次の教務課のメールにあるように
被告井形および被告池島らである。
⇒
被告井形および被告池島の共謀による原告の1部科目の2部重複開講を証明するメール
2.被告井形による特任申請辞退要請の認識(第3当裁判所の判断1(2)キ)
--------------------------- <原告が問題視する、当該部分> -----------------------------
キ 原判決20頁20行目から21頁5行目まで(項目ウ及びエ)を,次のとおりに改める。
「ウ 平成24年10月12日開催のカリキュラム検討委員会において,
控訴人が被控訴人井形に提出した「3ヵ年講義計画」についての検討が行われた。
その後,カリキュラム検討委員会の委員長であった被控訴人池島は,
検討の結果を被控訴人井形に報告した。
エ 被控訴人井形は、同月15日、控訴人に対し、カリキュラム検討委員会の総意として、
控訴人の担当する授業のほとんどは,不必要又は必要度が低いという結論になったと
述べ,控訴人の授業担当計画を特任教員推薦委員会に提出することはできない,
投票で否決されるような事態を避けたいなどとして、
特任教員への任用申請を辞退するよう求めた。
これに対して,
控訴人は,特任教員への任用申請を辞退する意思はなく,
投票で否決されることになっても構わないので
手続を進めて欲しいとの意向を示した。
この際,被控訴人井形が,
控訴人に説明した内容は,概ね次のようなものであった。(甲10,11)
--------------------------- <原告が問題視する理由> -------------------------------------
次の文より、
大阪高裁は、学部教授会の投票で特任任用が否決されるケースもあると判断していないかである。
「投票で否決されるような事態を避けたいなどとして,特任教員への任用申請を辞退するよう
求めた。これに対して,控訴人は,特任教員への任用申請を辞退する意思はなく,
投票で否決されることになっても構わないので手続を進めて欲しいとの意向を示した。」
(a) 経営学部教員の、特任教員任用規程の理解度
特任人事に係わった教員を除き、これを正しく理解している教員は殆どいないのが実情である。
その要因の1つは、定年退職者が極めて稀にしか発生しないこと。
今1つは、経営学部教員の離職率(他大学への移動を含め)が極めて高いことである。
その結果、前者では、濱本・千葉両教授の特任人事を進めた渡辺大介学部長(当時)でさえ、
「特任教員任用の窓口は、唯一、推薦委員会のみである」と規定する特任教員任用規程の内容を
正しく理解していない。
それほど、特任希望者は申請すれば、任用されるということが慣習化されていた。
後者は、次に示すように、
経営学部の良き伝統・文化が醸成される環境にあるかが問われる数字である。
⇒
2003年度在籍者は2012年度では28.9%、
2012年度の、退職率15.6%、新規採用率31.1%
2010年4月、新規程が制定されたが、当時、井阪理事長も重森学長も、
「人事については、従前と全く変わりなく」と合同教授会で発言、その趣旨にそって、
特任任用対象者は教学上の問題ではなく(既にこの観点で採用され、実績がある教員であること
から)、「大学人としてふさわしい人物」を特任任用の対象とすると規程変更されている。
⇒
(甲25)2005年7月1日、井阪理事長・重森学長の、合同教授会での発言の反訳文
⇒
(甲30)上記、音声データ
西口教授にセクハラで人権委員会に訴えられた人物、二宮教授の特任人事を
新規程ですすめた当事者である被告井形および被告池島は、2014年8月の尋問で、
旧規程から新規程に改訂されたが、特に変わったところはない、と答弁している。
その一方で、原告には、この新規程に抵触するとして、特任申請を却下するように勧めている。
これが被告らの大きな矛盾の1つであり、
今1つの矛盾は、
「学部教授会の投票で特任任用を否決できる」という、誤った解釈を
原告をはじめ、大阪高裁の裁判官に植えつけようとしたところである。
特任任用規程では、特任人事の推薦の窓口は、唯一、特任教員推薦委員会のみであって、
教授会が否決しても、理事会が否決しても、推薦委員会に戻され、
そこで、実態調査を行って、推薦するか否かが再審議する仕組みになっている。
被告井形および被告池島らが、この推薦委員会に原告の申請書類を提出できなかったのは、
被告らの計画的犯罪行為が暴露されるのを恐れ、
「書類の不備=原告の担当科目全て不要、不開講、
担当科目のない教員の特任人事はすすめられない」
として、推薦委員会に提出しなかったのである。
⇒
被告井形および被告池島らが、推薦委員会に原告の申請書類を提出できなかったのは何故か
重ねて、大阪高裁に伝えたいことは(今は、過去のことだが)、
学部の選挙で特任人事が否決されることはない、ということである。
経営学部を退職、他大学へ移動した教員、非常勤から、変質した学部運営に対し、多くの批判、
改善要望があることを、大阪高裁が判断されるにあたって、考慮されることを期待したかった。
3.被告池島報告の原告の担当科目の認識(第3当裁判所の判断1(2)エ)
--------------------------- <原告が問題視する、当該部分> -----------------------------
(ア)第2部科目として記載されている「情報ネットワーク論Ⅰ・Ⅱ」及び「情報バリューエンジニアリング」
「経営情報論」等は,学則(乙7)上は第2部の科目としては存在しないので,
特任教員への任用に際しては,担当科目として設けることはできない。
控訴人は,平成23年度及び平成24年度において上記の科目を第2部の時間帯にも
開講していたが,これは例外的措置として行われていたものであるから,
平成2525年度以降,これを継続する必要性は少ない。
(イ)「外国書講読I・Ⅱ」については,大学院進学者の入試対策であるところ,
成果が上がっていないことから必要度が低く,廃止するか,大学院の出題傾向に
明るい人が担当する方がよりふさわしいとして,
カリキュラム検討委員会で従前から廃止意見があった。
(ウ)「経営情報論」は,平成24年に経営情報学部が廃止されたことを考慮しても,
文化系の学部である経営学部においては,独立の科目としての重要度が低い。
(エ)「情報バリューエンジエアリング」については,
同科目が経営学部のカリキュラム体系上,必要か否かが明確ではない。」
ク 原判決21頁10行目及び12行目の各「推薦委員会」を,
それぞれ「特任教員推薦委員会」と改める。
ケ 原判決21頁19行目の「特任教員A」を「特任教員」と,同行目の「協議」を「報告」
と改める。
--------------------------- <原告が問題視する理由> -------------------------------------
この部分は、説明を除外する。
先頭に戻る
●「大阪高裁の判決とその分析・評価」に戻る
吉井が訴えた地位保全・確認訴訟へ
最初の画面に戻る