パワハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
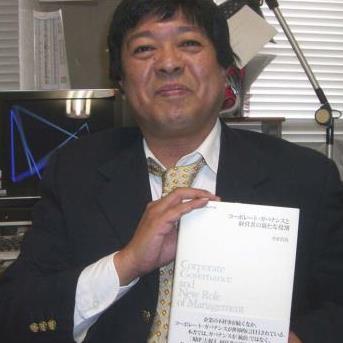
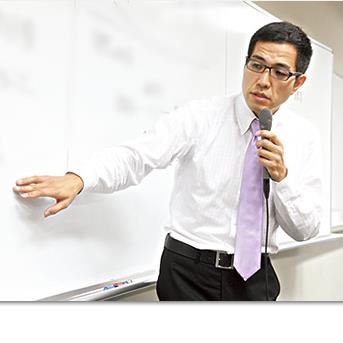


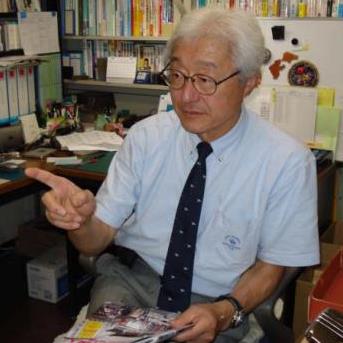


当該ホームページの公開期間は、パワハラ訴訟に主体的に関与した人物が、大阪経済大学を離れるまでとする。
再審請求: 〜 規定の誤解釈というミスがなければという反省のもとで 〜
最初に、再審高裁の判決に疑義を抱いたことを謝罪します。
この訴訟を、次の項目で概観することにする。
目 次
3.再審高裁判決:疑義その1:「過料の裁判が確定したとき」とは?
4.再審高裁判決:疑義その2:「先行判決等が変更されたという事実」とは?
5.再審高裁判決:疑義その3:「再審の訴え期間の算定方法」は?
1.再審制度との出会い
再審訴訟の目的は、特任人事における労使慣行の存在にある。
私が再審制度を知ったのは、
2015年10月1日、大学が名誉棄損等による1500万円の損害賠償訴訟の途中、
被告本人訴訟に切り替えた、2016年7月頃、準備書面作成中に再審制度を知り、
それを知った日から30日以内に訴えをしなければいけないことを知りながら、
敗訴すれば、1500万円の損害賠償に応じなくてはいけないため、
大学が仕掛けた損害賠償訴訟を優先したことを思い出す。
2017年10月12日に大阪高裁に準備書面(1)を出す頃、
民訴法338条を知り、その1項の6、7、9に該当する事由があることから
再審請求の道が開かれていると判断し、
2018年9月4日に大学による損害賠償訴訟の最高裁判決が出た頃、
再審請求の道は完全に塞がれているかを再度調べ、
民訴法第342条第1項の
「再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない」
という規定を次のように解釈し、再審請求した。
再審異議の申立期間30日間が経過しても、
・再審が出来る事実を知らなかった場合
・新しい証拠がある場合
それを知った日から5年間が再審の訴えの申立期間となる
という規定である(民訴法第342条第2項)。
私が再審の理由を知ったのが、2017年10月頃のため、
5年以内であり、再審請求が可能と判断したのである。
しかし、私が再審理由とした338条の事由と342条1項とがAND関係にあることを知らず、
この私の条文理解ミスが、再審高裁による再審請求の却下に至っている。
再審請求の却下、2019年7月17日の最高裁の却下により、
「労使慣行の存在」が完全に却下されたことは残念である。
(再審期間)
第342条
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
2 判決が確定した日 ( 略 ) から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
(再審の事由)
第338条
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
ただし、当事者が ( 略 )、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
( 略 )
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事 ( 略 ) が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、
有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決
若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
2.再審高裁に提出した、再審の理由
私は、再審理由を規定した民訴法第338条1項の6号、7号、9号に該当する
次の再審理由を挙げて再審請求している。
再審理由1)6号の事由では、
「特任人事における労使慣行を判断するうえでの重要な任用実績について、
大学は虚偽事実、データの捏造、判断不可能なデータを証拠としており、
「判決の証拠となった偽造又は変造されたもの」に該当します。
「再審の理由」の8頁以降にこの事実を記述しています。
⇒ 2018年10月30日大阪高裁提出の、「再審の理由」
再審理由2)7号の事由では、
「尋問における井形学部長・理事と池島副学部長兼カリキュラム委員長の虚偽供述」が、
「宣誓した当事者の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと」です。
訴訟の当事者である被告井形と被告池島は尋問で多くの虚偽発言をしていますが、
尋問での虚偽発言は、過料されないとの説明を受けていたが、
民訴法第209条より、被告井形と被告池島は過料されることが判明し、
再審の理由としたものです。
(虚偽の陳述に対する過料)
第209条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
再審理由3)9号の事由では、
相手方大学の虚偽陳述、虚偽供述、虚偽データを真正として、
特任人事における労使慣行の存在を否定した原審判決には、
申立人の控訴理由書に陳述した証拠甲23、甲24、甲25には言及していないため、
判決に最も影響を与える重要な証拠甲25も精査されていないと推認して、
これらの事由は裁判官の判断から抜け落ちている、
すなわち、「判断の遺脱」に該当する再審理由としています。
「再審の理由」の16頁以降、詳細に記述しています。
3.再審高裁判決:疑義その1:「過料の裁判が確定したとき」とは?
再審高裁の判決を信じているが、疑義もあり、それを述べます。
<再審高裁の判決:第2 当裁判所の判断の2>
再審原告は、… 略 … 原審判決が事実認定の資料とした再審被告大学作成の証拠は
ねつ造されたものであり、また、再審被告井形の本人尋問における供述は虚偽であった
などとして、民訴法338条1項 6号及び7号の再審事由があると主張する。
しかし、上記各号の再審事由については、
有罪の判決又は過料の裁判の確定等が再審の訴えに係る適法要件とされているところ、
本件においては、同事実の存在を認めるに足りる証拠はない。
したがって、上記再審事由に係る再審の訴えはいずれも不適法である。
<疑義その1:「過料の裁判が確定したとき」とは?>
再審高裁は、罰すべき行為について「有罪の判決があったか、過料があったか」、
この再審適法要件の事実がないため、再審理由があっても再審請求できないと判示している。
民事訴訟法第338条の1項の
6号 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
7号 … 略 … 又は宣誓した当事者 … 略 … の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
2項の、
前項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、
有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、… 再審の訴えを提起することができる。
疑義その1は、民訴法第338条の2項の「過料の裁判が確定したとき」の解釈である。
私の見解では、原審「地位確認訴訟」では井形と池島の共同不法行為に対し、
80万円の科料が確定しており、再審の訴えは可能となる。
この条文には主語がないため、
その事実さえあれば、原告も被告も再審請求可能と判断したが、
科料された側のみ、再審請求可能ということだろうか?
再審高裁に望むことは、
「同事実の存在を認めるに足りる証拠はない」とするところを
第3者にわかるように説明されたい、と希望するのみである。
⇒ 2019年3月28日 再審高裁の、判決
4.再審高裁判決:疑義その2:「先行判決等が変更されたという事実」とは?
再審高裁の判決を信じているが、疑義もあり、それを述べます。
<再審高裁の判決:第2 当裁判所の判断の3>
再審原告は、
前訴判決の言渡し後の再審原告と再審被告大学間の別件訴訟
及び草薙信照と再審被告との間の別件訴訟における
各判決で認定された事実が、
前訴判決で認定された事実と異なるなどとして、
民訴法338条1項8号の再審事由があると主張するものと解される。
しかし、同号は、
前訴判決の基礎となった先行判決等が変更されたという事実を
再審事由とするものであり、
前訴判決の認定事実が後にされた
別件訴訟における裁判の認定事実と異なる場合は、
同号には該当しないと解される。
したがって、再審原告の上記主張は理由がない。
<疑義その2:「先行判決等が変更されたという事実」とは?>
次の民訴法第338条の1項8号をどう解釈するか、私には極めて難解な法文である。
民事訴訟法第338条の1項の
8号 判決の基礎となった民事 … の判決 … が後の裁判 … により変更されたこと。
私は、訴訟の時間軸でこの条文を次のように解釈した。
判決の基礎となった民事の判決とは、私が訴訟を起こした地位確認訴訟の判決を指す。
後の裁判により変更されるとは、私の訴訟確定後、大学の賠償請求訴訟の判決により、
私の地位確認訴訟の判決が何らかの修正という事態に陥ったと解釈した。
「先行判決等が変更されたという事実」は、
このような訴訟の判断基準となる過去の判決、という意味かもしれない。
私には、再審高裁の判示の意味するところは凡そ推認されるが、
私の論理の誤りを正すためにも、再審高裁の丁寧な説明が期待される、と思う。
5.再審高裁判決:疑義その3:「再審の訴え期間の算定方法」は?
再審高裁の判決を信じているが、疑義もあり、それを述べます。
<再審高裁の判決:第2 当裁判所の判断の4>
再審原告は、基本事件において提出した重要な証拠(甲23〜25)について、
「判断の遺脱」があるとして、民訴法338条1項9号の再審事由を主張するものと解される。
そこで検討すると、再審の訴えは、当事者が判決の確定した後
再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならないところ
(民訴法342条1項参照)、
再審原告は、本件確定判決の正本を受け取ったときに
判決に影響を及ぼすべき重要な事項について
判断の遺脱があったことを知ったものと推認される。
しかるに、本件再審の訴えは、
本件確定判決の確定の日である平成27(2015)年5月8日から
30日の不変期間経過後の平成30(2018)年10月30日に提起されている。
そうすると、上記再審事由に係る再審の訴えは不適法であるというべきである。
<疑義その3:「再審の訴え期間の算定方法」は?>
再審の訴え期間については、342条1項の
「 … 再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない」より、
大学による名誉権侵害等損害賠償請求事件で、
被告本人訴訟に切り替えた2016年7月頃に再審制度を知り、
2017年10月12日に、同事件の大阪高裁に準備書面(1)を出す頃、
民訴法338条1項9号の「判断の遺脱」というを知ったため、
342条1項の不変期間より、2017年11月11日頃が再審の訴え期間となる。
したがって、再審高裁の、2015年5月8日より30日の不変期間は誤りではないかと思う。
しかしながら、
再審理由「判断の遺脱」は、再審の訴え申立期間を充たさないため、再審請求は却下となる。
6.感想:再審請求のハードルの高さ
再審請求失敗の最大の要因は“無知”に尽きる。
今現在、条文の第1項と第2項は独立か、ANDか、ORの関係かが不知である。
そのため、民訴法338条と342条の解釈ミスにより、
再審請求という狭い入り口にも辿りつけなかった。
これが、次の条文の「判断の遺脱」のもとで、「特任人事における労使慣行の存在」を
再検討していただくという機会を失った最大の要因である。
民事訴訟法第338条の1項の
9号 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
「判断の遺脱」とする根拠は、
地位確認訴訟において、大学が捏造した特任教員任用実績の情報をもとに
大阪地裁が、「特任人事における労使慣行が存在しない」という表を自ら作成し、
誤判決している、と私が強く確信する状況のもとで、
大阪高裁にその判決を覆す3つの証拠を提出したが、
大阪高裁は、その3つの証拠に触れることなく
「特任人事における労使慣行は存在しない」と判決を下している。
すなわち、「判断の遺脱」であり、その3つの証拠とは、以下の証拠である。
甲23は、大学の最高経営責任者である井阪理事長と教学の長である重森学長の
「特任人事における労使慣行の存在」は、心情の吐露であり、経営理念に当たる。
甲24は、山田学長補佐が次の2つの事由を語る私との私的会話である。
・大学が特任教員任用制度を規定した時の、
定年を70から67歳にした時に共有されていた特任人事の考え方
・経営学部執行部はカリキュラム委員会の規程を逸脱する行為をし、
教授会で議論させずに私の特任人事を闇に葬ろうとしている。
甲25は、草薙副学長・理事が次の2つの事由を語る私との私的会話である。
・大学の理事会が理事長を代行する北村實総務担当理事の専横により、
正常な意思決定がなされていないこと
・井形経営学部長・理事兼特任教員推薦委員は、学長執行部のアドバイスを聞かず、
特任規程に反する不法行為をしているという内容である。
この重要な3つの証拠が大阪高裁の判決では、全く判断された痕跡がないことから、
この誤判決をもとに、再審請求の申立期間内であれば、
「特任人事における労使慣行の存在」を再検討していただけたのでは、と
後悔している事由である。
無知とする2つ目は、「3審制」を採用されているが、実質、「2審制」で、
地裁と高裁が「事実審」、最高裁が「法律審」のため、
最高裁に「事実」に該当する事由を上告しても却下されるのみ、という無知である。
したがって、再審高裁が再審請求を却下した折、最高裁へ上訴するに当たり、
民訴法338条に適合する新たな再審理由として、次の2つに気付き、
特別抗告理由書に表記したが、最高裁は却下の理由を示さず、棄却している。
・特任教員任用規程(新規程)の変造である。
平成24年9月28日の教授会で
井形学部長と北村総務担当理事が変造した規程を説明する。
・「経営学部教授会規程」の変造である。
平成23年11月11日の教授会で強行採決した、
欠席者の投票を認める「経営学部教授会決議方法」
という1年限りの試行という規程
これらは、刑法第159条3項(虚偽文書の作成、権利、義務に関する文書を偽造、
又は変造した者に対する罪)と刑法第161条(偽造私文書を行使した場合の罪)に
抵触する再審理由と判断するが、
再審高裁に再審請求する時点であれば、申立期間内となり、
再審訴訟が実現したのかも知れない。
いずれにしろ、「無知」であったことを反省し、
一時期、
再審高裁の判決に疑義を抱いたことをお詫びいたします。
7.再審訴訟における裁判資料一式
以下に、再審訴訟における裁判資料一式を掲載する。
⇒ 2018年10月30日大阪高裁提出の、「再審の理由」
再審理由の3つの事由を知った日より30日以内が再審請求申立期間と気付かず、
338条を独立の条文と解釈したことによる手続きミスの存在のまま申請した。
⇒ 2019年3月28日 再審高裁の、判決
手続きミスを指摘される。「判断の遺脱」を事実と確信する立場から、
申請期限切れ対策として、新たな再審申請理由を探し、
最高裁に提出したが、この時点では「事実審」でないことに気付かなかった。
⇒ 2019年4月22日 抗告許可申立理由書
再審高裁判決に対する抗告許可申立理由を陳述している、
再審請求者の再審理由の総括である。
⇒ 2019年4月22日 特別抗告理由書
再審理由を総括し、
さらに新たな刑法に抵触する不法行為などを特別抗告理由としている。
しかし、最高裁は「法律審」であることを忘れていた。
⇒ 2019年7月17日 最高裁: 調書(決定)
主文: 本件抗告を棄却する