パワハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
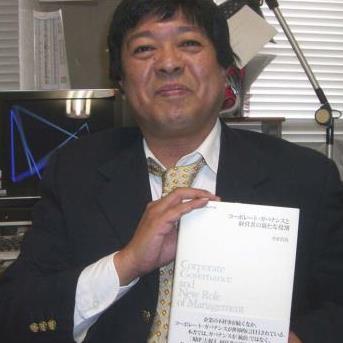
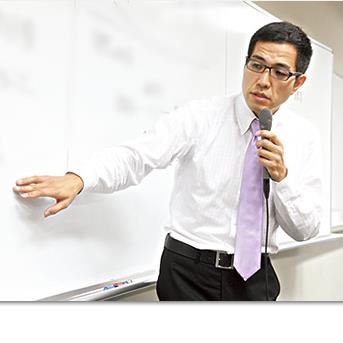


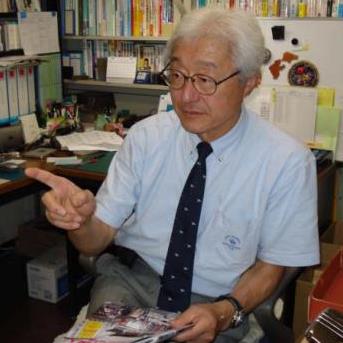


当該ホームページの公開期間は、パワハラ訴訟に主体的に関与した人物が、大阪経済大学を離れるまでとする。
※ 不法行為抑止と情報公開の限度に供する下記HPの紹介:
公開することが公共の福祉の追求に至る、その公開性による公共性のもとで、
私の公開したパワハラ訴訟から、訴訟の大切さを疑似体験してください。
大 阪 経 済 大 学 との パ ワ ハ ラ 訴 訟
〜 私がめざしたものとは 〜
私が、何故、大阪経済大学とのパワハラ訴訟の全貌をWEB公開する行動を選択したのか、
その根底の1つに、私が生きてきた社会での倫理観からは想像し難い、
狭い人事交流のもとで構築される組織にありがちな、
大学という閉鎖社会に潜在する「社会的矛盾」があります。
今1つは、地位保全および地位確認を求めた大阪地裁での訴訟の印象に起因する、
「裁判を受ける権利」と「法の下の平等」に感じるところの疑問です。
ここでは、それら「矛盾」「疑問」について、
下記の項目で述べることにより、大阪経済大学とのパワハラ訴訟の総括とします。
パワハラ訴訟〜 私がめざしたものとは 〜 目 次
(2−1)「裁判官も弁護士も人間であり、判決も人間が下したものである」
D)地位確認等請求事件における大阪経済大学代理人弁護士の行動
1.「社会的地位のある方々にみられる社会的矛盾」
社会的矛盾、その1つは、「社会的地位のある方々にみられる社会的矛盾」です。
最初に、これについて述べます。
(1−1)当大学の責任ある立場の方々にみられる社会的矛盾
経営責任のある理事会構成メンバーの方々、
ここでは、理事長を例にして述べることにします。
理事長に選出された方々は、
既に社会的地位が確立した、著名な、社会に影響力を有する方々です。
その一人の理事長に、私は、経営学部執行部の不法行為を問題視し、
大学の行動規範はかくあるべき、と問題提起しましたが …。
理事長交代の直前であったため、
うすうす問題があることは察知されていましたが、
波風を立てずに、任期を終えられました。
これに対し、佐藤武司理事長は、
被控訴人井形浩治、被控訴人池島真策の
故意による共同不法行為が確定したにもかかわらず、
その地位を利用して私の人格を全否定する民事訴訟を仕掛けました。
草薙裁判は、この理事会の行動規範の矛盾を鮮明にした訴訟です。
佐藤武司理事長および理事会執行部は、私による地位確認訴訟の敗因を、
私が草薙副学長・理事に個人的に相談した事由にあるとして、
年俸10%減などの懲戒処分を草薙教授に科したことに起因する裁判ですが、
この草薙裁判の大阪地裁の和解内容をみると、
大学は、草薙教授に対する懲戒処分を撤回し、かつ、
彼の名誉を回復すること、という内容になっています。
草薙裁判は、和解(現職の草薙教授の立場では穏当な結末が求められます)ですが、
実質敗訴した理事会は、
不法行為の当事者である、経営学部長・理事の、井形浩治と池島真策には、
「故意による共同不法行為」という判決が確定し、
大学の名誉を著しく損なった張本人であるにもかかわらず、
大阪高裁判決を考慮せず、即ち、無視し、懲戒処分することなく、
現時点においてもなお、懲戒処分されたとは聞いていません。
最高意思決定機関である理事会という《 組織の権力構造 》、
理事長、あるいは、理事という《 職位=権威 》がもたらす、「社会的矛盾」、
これを第3者にわかる形で問題解決する方法は、
意思決定過程を公開する公開性のもとで、
公共の福祉を追求する公共性が照応する、と解して、
情報公開による説明責任を果たすアプローチが有効と、私は確信しています。
社会の秩序を護るために、情報発信すること、その結果責任は自らが負う、
この考え方を具体化する手段の1つがホームページであり、
インターネット社会のニューメディアに求められる機能の1つとして、
公開性による公共性の追求、成立がニューメディアの使命となる
と私は主張します。
(1−2)当大学の経営学部執行部にみられる社会的矛盾
執行部の人物批判をすることがここでの目的ではありません。
執行部は、経営学部長、副学部長兼カリキュラム委員長、学部長補佐で構成され、
緊密に、学部運営に係わる全ての必要事項を打ち合わせ、
教授会運営しています。
この執行部という職位のもつ基本機能を逸脱する行為が、
私への不法行為にみられるように、常態化している場合は問題です。
この経営学部執行部は、
・教授会執行部という、中間管理職としての顔、
・専門分野の研究成果を学生に教育するという、教育者としての顔、
・専門分野の研究をし、成果をあげるという、研究者としての顔、
それぞれの顔を併せ持っており、
それぞれに求められる必要機能を達成し、調和を図ることが求められます。
したがって、それぞれの顔に反する行為がある場合、
社会的矛盾が生起することになります。
私の訴訟に関係した方々(含む、大学による名誉権侵害等賠償請求事件)では、
北村實、井形浩治、池島真策、木村俊郎は、
経営学部教授会執行部、学部長という中間管理職の被雇用者であり、
雇用者側の立場にたつ理事でもあるという2面性を有しており、
研究・教育の観点では、
北村實、池島真策、木村俊郎は、法学を研究し、
当該分野の教育をとおして、法令順守を指導する立場にあり、
井形浩治は、下記を研究・教育する教授です。
CSR(corporate social responsibility 企業の社会的責任)
学部長補佐の立場にあった教員には、
吉野忠男、田中健吾、高原龍二が名前を連ねています。
在職時の私は、彼らの採用にはアンタッチャブルのため、ネット情報によれば、
吉野忠男は、法学と経営学の修士を修めた優秀な教授であり、
田中健吾は、産業心理学などの担当教授で、臨床心理士の立場から
「職場のメンタルヘルスとハラスメント」と題する講演などをしています。
高原龍二も臨床心理士で、産業・組織心理学担当の准教授で、
組織における心理的問題の改善を研究テーマとし、
メンタルヘルスと社会改善、産業ストレスに係わる講演などをしています。
このように高学歴で、専門性の高い研究をされている方々が、
私の特任人事および訴訟の過程では、
次に示す、反社会的と推認される行為、矛盾する行為を平然と行っています。
・北村實と田中健吾は、
経営学部教授会規程に反する、教授会欠席教員の投票を認める動議を提出、
1年限りの試行という条件のもとで強行採決しています。
この動議は、「私文書偽造・変造」という刑法犯の疑義があります。
・北村實、井形浩治、池島真策は特任教員任用規程およびカリキュラム委員会規程の
偽造・変造を行い、彼らも刑法犯の疑義ある行為を遂行しています。
・井形浩治は、特任教員推薦委員会に私の申請書類を故意に提出せず、
教授会で「不受理になりました」と報告、議論を拒否するという、
特任教員任用規程の手続きに反する行為を行い、その行為を正当化しています。
・池島真策カリキュラム委員長は、カリキュラム検討委員会で
私の担当科目を全て不必要であり、不開講とする。
担当科目のない教授の特任教授は認められない、
これがカリキュラム委員全員の総意である、と
本来のカリキュラム委員会規程を逸脱する行為を正当化しています。
・私の地位確認訴訟の尋問では、井形浩治および池島真策は虚偽陳述をしています。
これは、民訴法第209条第1項(宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、
裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する)に抵触しています。
・草薙裁判で、証人尋問に立たされた北村實の虚偽陳述は、当事者ではないため、
刑法169条(法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、
3か月以上10年以下の懲役に処する)に抵触、偽証罪に問われる行為です。
・高原龍二は、
私の3回生のゼミ生の指導を引き受けてくださった方ですが、
教授会で、三島先生お一人が自主的に、
私のゼミ生を何名か引き受けますと発言されたのとは異なり、
ゼミ生の「バラバラになりたくない」との希望と、執行部の意向のもとで、
私のゼミ生全員を引き受けられたと聞いています。
経営学部に着任後、直ぐに、学部長補佐に就かれ、
執行部の一員として、北村實、井形浩治、池島真策らが
どのように私の特任人事を妨害したのかを知り、
その一方で、引き継いだ私のゼミ生からは、
直接、偏りのない、私に係わる生の情報を入手し、
かつ、第3者評価となる、私の地位確認訴訟の大阪高裁判決
「井形浩治、池島真策の故意による共同不法行為」の確定の下で、
大学の損害賠償訴訟に必要な証拠、陳述書を大阪地裁に提出しています。
「組織における心理的問題の改善」を研究テーマとする臨床心理士が、
大阪高裁の客観的な判断、「故意による共同不法行為」を否定し、
「組織の一員としても、教育者としての立場からも、
私は吉井氏に猛省を促したいと思います」と陳述するところに、
研究者の顔、教育者の顔、組織責任者の顔を垣間見させる
「不調和」という矛盾ある行為の存在を指摘します。
また、
情報通信総合研究所の客員研究員、羽衣学園短期大学の非常勤講師をしていた私に対し、
北村實は、
理事会は非常勤講師などを認めない方向で進めており、早急に辞めるように、と、
指示され、私は、閉鎖的な大学だなと寂しい思いをしながら、辞めたところ、
私を名誉権侵害などで訴えた佐藤理事長の陳述書には
故意による共同不法行為が確定している井形浩治の、
芦屋大学非常勤講師採用に悪影響を与えているといった記載があり、
田中健吾、高原龍二のWEB情報には、
多くの大学の非常勤講師をはじめ、学外での活動をしている記載があります。
このような「社会的矛盾」の生起には、様々な要因が考えられますが、
「大学の自治」を隠れ蓑にする不法行為の類には、
問題解決の最終的な手段として、前述した、私のアプローチが有効と思われます。
-----------------------------------------------------------------------------------------
この私の主張のもとで、
公開性による公共性の追求手段としてのHPが受容され、
公益性に寄与することを祈ります!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
2.裁判の印象を語る
私の理性の世界では、悪事を働けば、罪に服すべし、
すなわち、信賞必罰は、人としての摂理でしたが、
現実は、権力や組織力、資金力、人脈など、
力あるものが、恣意的に、優位に誘導する歪み、リスクのある世界であり、
それを律する「法のもとの平等」の歪みと感じています。
この観点にたって、私の体験した裁判の印象を述べたいと思います。
(2−1)「裁判官も弁護士も人間であり、判決も人間が下したものである」
「人間は不完全な存在であり、
様々な環境要因によって、常に「真実」に至るとは限らない」という立場にたって、
私が訴えた訴訟、地位保全および地位確認訴訟は、
裁判官、代理人弁護士のもとで、
唯一の答え、「真実」に至ったのかを考察することが、ここでの目的です。
最初に、裁判官および弁護士の行動規範について述べます。
A)裁判官の行動規範
裁判官は、
国家公務員倫理法や最高裁判所規則の定める倫理規範の順守などが求められます。
司法制度改革審議会での「国民が求める裁判官の資質・能力」に関する議論を紹介します。
「何が事案の真相であるかをを見抜く洞察力や、事実を的確に認識し、把握し、
分析する力を持った裁判官」、
「人の意見をよく聴き、広い視野と人権感覚を持って当事者の言い分をよく理解し、
なおかつ、予断を持たずに公正な立場で間違いのない判断をしようと努力する
ような裁判官」 ……
B)弁護士の行動規範
弁護士は、弁護士職務基本規程の順守が求められます。
この規程の一部を下記に示します。
(使命の自覚)
第1条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と
社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
(司法独立の擁護)
第4条 弁護士は司法の独立を擁護し
司法制度の健全な発展に寄与するように努める。
(信義誠実)
第5条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、
誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(裁判の公正と適正手続)
第74条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
(偽証のそそのかし)
第75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、
又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
裁判官および弁護士に求められる行動規範を理解したうえで、
私が地位保全・地位確認を求めた訴訟の結末が真実に至ったのかを考察します。
C)地位保全仮処分命令申立事件における裁判官の行動
(a)裁判官の行動
2013年2月25日に仮処分申立を申請、3月13日と27日の2回の審尋で、わずか15日間で、
私が訴えている保全の必要性の状況証拠も、
経営学部執行部によるパワハラ行為も確認することなく、
保全の必要性はないとの判断のもとで、申立の却下が口頭で同意=決定され、
民事裁判で争うよう指示される。
(b)審議内容
2013年3月13日の第1回審尋では、裁判官は、
特任教員任用の労使慣行が存在する、という主張では、
仮処分の申立にあたらないと発言され、
労使慣行があるかということに結び付けた
損害賠償請求訴訟で解決したほうがよいのでは、と発言される。
3月27日の第2回審尋では、裁判官は、
裁判で争うようにと、地位保全仮処分命令申立を取り下げを諭される。
------------------------------------------------------------------------------------
<参考> 私と、里上教授の地位保全仮処分命令申立事件の対比
・特任任用手続き:
里上教授は、一旦特任教授として承認されたが、学長選挙管理委員会委員長の
立場で、渡辺前学長の選挙参謀をした責任を問われて、
2005年3月22日、特任教授採用取り消しとなり、
3月31日、仮処分の申立をしています。
吉井は、井形浩治学部長・理事と池島真策の故意による共同不法行為のもとで、
吉井の申請書を推薦委員会に提出しないで、教授会で、不採用になりました、
と報告、特任教授の機会を奪ったため、2013年2月25日、申立てをしています。
・申立却下までの期間:
里上教授のケースでは、3月31日仮処分の申立てをし、4月11日に第1回審尋、
7月4日、申立ての却下が決定、約3ヵ月弱の審尋の結果、却下されています。
吉井のケースでは、2013年2月25日仮処分を申立て、3月13日に第1回審尋、
3月27日の第2回審尋で申立てを却下、僅か15日間の審尋という異常さです。
・評価:
里上教授の審尋と比較して、
吉井の審尋は、「審議不要、結論ありき」という様相を呈しています。
------------------------------------------------------------------------------------
(c)裁判官の行動を評価する
地位保全の必要性のハードルが高いことから、「保全の必要性無し」と判断されたようですが、
この急な、わずか15日間、2回の審尋で、保全を求める状況証拠の確認もなく、
申立を却下した裁判官の行動に不自然さを感じています。
「保全の必要性」の確認もしなかった不自然さは、
その後の、私の地位確認訴訟での大阪高裁判決および
大学が私を名誉権侵害等で損害賠償を求めた訴訟の、大阪地裁・大阪高裁判決が、
「地位保全裁判官の行動」の不自然さを立証しているのではないでしょうか?
------------------------------------------------------------------------------------
〜 「地位保全裁判官の行動」の不自然さを立証する、判決や証拠等 〜
地位確認訴訟の大阪高裁の判決および大学が私を名誉棄損などで訴えた訴訟の判決では、
私には特任教員の申請資格があり、
執行部、特に、井形浩治および池島真策の故意による共同不法行為による妨害であり、
井阪理事長と重森学長の、合同教授会での発言
「人事における労使慣行は変わらず」の証拠からも、
地位保全の必要性は精査されるべきであったと推認されます。
経営学部執行部のパワハラで、
特任任用規程の変造、
カリキュラム委員会規程の変造、
その結果、私の担当科目は不要で、担当科目のない教員の特任は認められないとして、
推薦委員会に私の申請書類を提出せず、「申請は却下された」と報告しています。
------------------------------------------------------------------------------------
(d)裁判官の行動規範からみた結論
「何が事案の真相であるかをを見抜く洞察力や、
事実を的確に認識し、把握し、分析する力を持った裁判官」という観点で
問題があったことが認識されます。
これを回避する有効な手段は、
「複数の裁判官による合議制」です。
私が、本人訴訟に切り替えて闘った印象では、
準備書面で真実と信じるべき事実を陳述すれば、
裁判長および2名の裁判官の合議制のもとで、誤認識による誤判決は皆無です。
地位保全仮処分命令申立も、地位確認訴訟の大阪地裁も、裁判官が一人であったため、
大阪経済大学の訴訟の巧みさに、誤判断、誤判決へと誘導されています。
D)地位確認等請求事件における大阪経済大学代理人弁護士の行動
私が大阪地裁に訴えた、「地位確認等請求事件」での
大阪経済大学代理人弁護士の行動を考察します。
(a)大阪経済大学と代理人弁護士との関係
俵法律事務所の代理人弁護士は、
大学の訴訟、例えば、里上教授の地位保全仮処分命令申立事件の代理人弁護士でもあり、
大阪経済大学の諸規程に通じている方であり、大学の顧問弁護士ではないかとみています。
(b)大阪経済大学代理人弁護士の行動
代理人弁護士は、
大阪経済大学が、里上教授の特任教授保全を求める訴訟で、
特任人事には労使慣行は存在しないとする虚偽データを大阪地裁に提出しましたが、
私の地位確認訴訟においても、
この虚偽データの個人名をマスキングして、個人の特定不能にして提出しています。
この行為は、里上裁判を担当されているため、「私は知らなかった」とは言えない事実で、
弁護士職務基本規程の「第75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、
又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。」に反しないでしょうか?
今1つ、北村グループの執行部による、特任教員任用規程、経営学部教授会規程、
経営学部カリキュラム委員会規程の変造に関し、
大学の諸規程に精通されている立場から、
大学の準備書面の虚偽陳述を黙視しつづけることは、
弁護士職務基本規程の
「第74条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。」
に反しないでしょうか?
(c)代理人弁護士の行動規範からみた結論
前述の代理人弁護士の行動は、
通常の訴訟当事者では、里上教授の地位保全訴訟の内容など知りえない。
多分、それを前提とした「情報格差」を利用した訴訟行動であり、
(信義誠実)第5条は、顧問弁護士の立場から、
大阪経済大学の利益に供するというところに関心があると推認されます。
私が弁護士であれば、このような選択はしませんが。
(2−2)「裁判の生産性」
A)訴訟期間の短縮とデシジョン・ツリー
私が経験した訴訟期間は、下記3つの大阪地裁では、審尋期間は平均439日、
結審後、判決までの期間は平均100日、全体で539日費やされています。
大阪高裁は、2つの事例ですが、審尋期間は143日、
結審後、判決までの期間は平均88日、全体で231日費やされています。
これを参考に、1つの訴訟で、第一審、控訴審まで訴訟すると
少なくとも2年以上の歳月と労力、経費が
裁判所および、訴訟の当事者双方に発生します。
したがって、これを半減、それ以下の時間で訴訟を終審させる工夫をすること、
そのような改善をすべきです。
そのために、私なりの方法を提案したいと思います。
訴訟期間の実績データ
地位確認等請求事件:審尋期間、428日、判決期間、53日
2013年6月7日の吉井の訴状に始まり、
2014年8月8日の被告大学準備書面(5)で審尋終了、
2014年9月30日、大阪地裁判決
大学による名誉権侵害等賠償請求事件:審尋期間、469日、判決期間、154日
2015年9月29日、大学の訴状に始まり、
2017年1月10日、大学の第6準備書面で審尋終了、
2017年6月13日、大阪地裁判決
名誉棄損訴訟:大学を訴える:審尋期間、420日、判決期間、94日
2018年10月30日、吉井の訴状に始まり、
2019年12月23日、吉井の準備書面(7)で審尋終了、
2020年3月26日、大阪地裁判決
地位確認等請求控訴事件:審尋期間、117日、判決期間、80日
2014年10月10日、吉井の控訴状に始まり、
2015年2月3日、大学の附帯控訴理由書(補充)で審尋終了、
2015年4月23日、大阪高裁判決
大学による名誉権侵害等賠償請求控訴事件:審尋期間、169日、判決期間、83日
2017年6月22日、吉井の控訴状に始まり、
2017年12月7日、吉井の準備書面(3)で審尋終了、
2018年2月27日、大阪高裁判決
B)デシジョン・ツリーの導入
(1) 裁判官は、いわゆる医者の立場で、
訴状をもとに、現在の民法・刑法などでの訴えの適切さを事前診断します。
(2) 裁判官は、原告(含む代理人)と被告(含む代理人)との3者協議のもとで、
訴訟の状況から、原告と被告の主張およびリスクの認識のもとで、
訴訟対象に適合するデシジョン・ツリーを選択します。
(3) 裁判官は、法令を執行する司会者の立場で、このデシジョン・ツリーの流れにそって、
法令にもとづいて、原告に求められる証拠は何かを明示し、提出を命令します。
被告にも同様の観点で、反証すべき証拠は何かを明示し、提出を命令します。
(4) 裁判官をはじめ、原告、被告は、タイムラグのもとで、証拠を精査したうえで、
裁判官の司会のもとで、デシジョン・ツリーの充たすべき要件にそって、
原告および被告の陳述および証拠の真正を、3者協議による精査をします。
(5) ここで、(3) と (4) を繰り返し、
デシジョン・ツリーの全てのステップを充たせば、原告の勝訴となり、
途中でストップすれば、却下・敗訴となります。
このデシジョン・ツリーのメリットを下記に表記します。
- このデシジョン・ツリーは
法令を国民に明示するもので、
法令を不知な方々も、裁判官の診察のもとで教科され、
原告、被告、代理人弁護士の技量、駆引きを排除することが可能となり、
- このデシジョン・ツリーの各ステップの必要項目で要求される証拠類は、
第3者協議のもとで、有用な証拠か、虚偽はないか、の疑義が排除されます。
- 判決は、このデシジョン・ツリーが
定められた法令の厳正な手続きと同値であることから、
ツリーの停止したステップが判決となり、判決の表記が簡潔・明瞭になります。
法律の専門家は、優れたデシジョン・ツリーの作成をすることにより、
現在の法令の不備、曖昧さを解消する対象が明示され、
必要な法整備を促す効果が期待されます。
いわゆる、法令に求められる「機能保証」が達成されることになります。
この提案は、VE(Value Engineering)の機能保証の考え方であり、
デシジョン・ツリーは、日本VE協会が推奨するの機能系統図の応用です。
デシジョン・ツリーのイメージは、
訴状提出者の内容をもとに、現行法規のもとではどのような判決に至るかを、
目的(=要望する判決)を明確にして、それを充たす必要要件・制約条件を列挙する。
列挙したそれぞれの必要要件・制約条件を目的に、それを充たす要件等を列挙する、
といった意思決定構造のフローチャートを作成したものです。
3.感 想
私の後半生の貴重な8年を大阪経済大学とのパワハラ訴訟に費やしたことは、
私が成し遂げたかった多くの業務を前に後悔の日々を送っています。
訴訟をして、不知ほど恐ろしいものはなく、
法律に精通し、良心的な方の協力を受けることの大切さを痛感します。
私の訴訟の後悔するところは、
地位保全仮処分命令申立訴訟で、地裁が却下した時点で、
刑事訴訟しなかったことです。
その理由は、不知で、民法での問題解決は主に「損害賠償」であり、
私が求めていたのは、不法行為の犯罪を立証することにあったため、
即、刑事訴訟しなかったことが後悔するところです。
刑事訴訟として訴える証拠、
私文書偽造罪、名誉棄損罪など、沢山あったにも関わらず、
私が刑法を理解した時には、
公訴時効という規定のもとで、
断念せざるをえなかったことが唯一の後悔です。
この公訴時効範囲内は、「訴訟詐欺」しかなく、
その疑義はあるものの、顕在化させ、勝利に導くことは不可能に近いと判断し、
大阪地検に提出したものの、断念しています。
⇒ 2020年1月20日、告訴状
⇒ 同、証拠説明書
------------------------------------------------------------------------------------
私は、訴訟で何を得たのでしょうか、
訴えた、故意による共同不法行為者である、北村實、井形浩治、池島真策、
この3名の不法行為に加担した方々は
現在、どのような気持ちで、
私の裁判を見聞し、
私のホームページを閲覧されているのでしょうか?
万葉集に、次の和歌があります。
この和歌は、私が畝傍高校在学時に、高校の前の本屋さんで立ち読みをし、
2人の歌人の心のニュアンスを理解したうえで、
その後の私の生き方の糧にしてきた2首、それが語りかけてきます。
大伴家持
ますらをは 名をし立つべし 後の世に 聞き継ぐ人も 語り継ぐがね
山上憶良
士やも 空しかるべき 万代に 語り継ぐべき 名は立てずして
------------------------------------------------------------------------------------